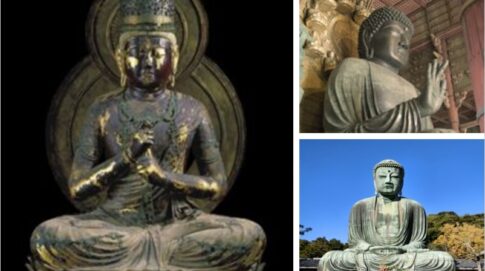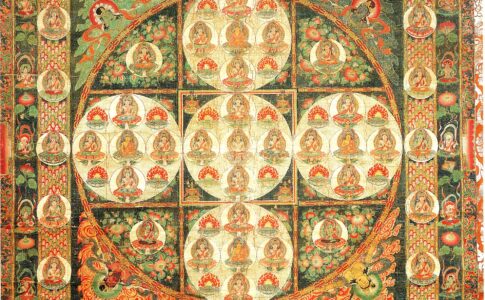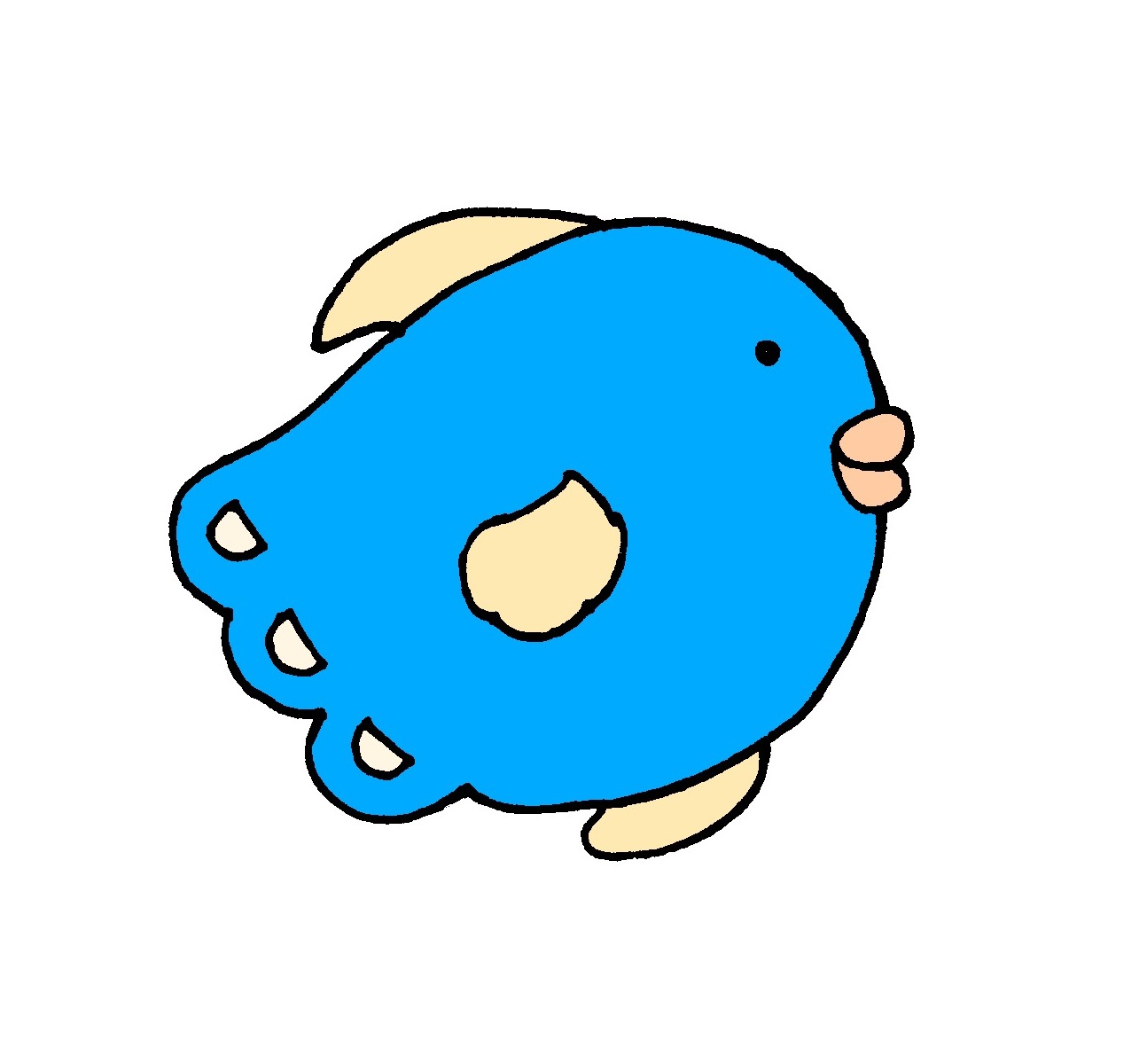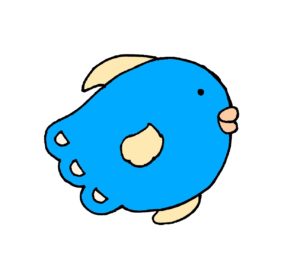
こんにちは、はてはてマンボウです。
今回は「神社とお寺の違い」シリーズ第3弾。

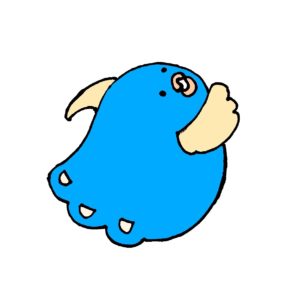
神社とお寺の違い② はて神社とは その2:鳥居と建築様式
前の記事を見たい人はこちらをチェックしてくれ~
それじゃあ、今回からはお寺について見ていくよ。
.jpg)
梓
目次
何を拝むのか
お寺で拝む対象は「仏」だ。
.jpg)
梓
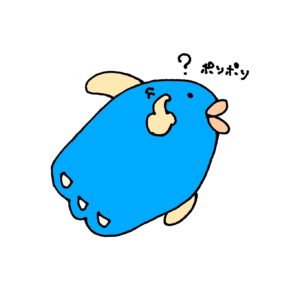
「神さま」と違って、仏さまは想像つくまぼねえ。
たしか、種類もいっぱいあったような。
仏さまの種類は大きく分けて
如来
菩薩
明王
天
の4種類だ。
.jpg)
梓

釈迦如来(飛鳥寺、奈良)
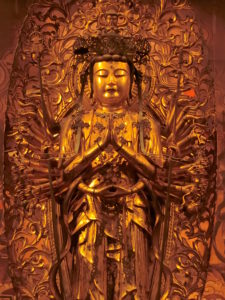
千手観音像(仁和寺、京都)

降三世明王像(仁和寺、京都)

金剛力士像(東大寺、奈良)

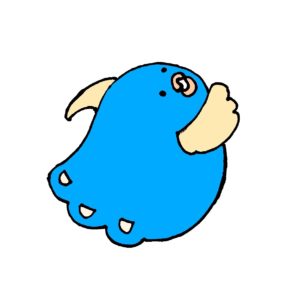
今日からわかる仏像の見分け方
仏像の種類についてもっと知りたい人は、こちらの記事を見るまぼよ~
参拝方法
さて、お寺に着いたら、以下の流れに注意してお参りしよう。
.jpg)
梓
まずは山門を通るけど……

山門「仁王門」(長谷寺、奈良)
- 入口の総門や山門で、まずは合掌
- 入口の一段高くなっている「敷居」は踏まずにまたいで通る。
手水舎でお清め

手水舎(四天王寺、大阪)
手水舎がある場合はここで身を清めよう。基本的な作法は神社と同じ。
.jpg)
梓
- ①右手で水を汲む
- ②左手を清める
- ③右手を清める
- ④左手に水を溜める
- ⑤左手の水で口を清める
- ⑥残りの水で柄杓の柄(え)を清める
拝む

本堂(善水寺、滋賀)
本堂では、左右の手のひらを合わせて、一礼しよう。
.jpg)
梓
お寺でゴーン! お寺と言えばやっぱり釣り鐘!?

梵鐘(青蓮院門跡、京都)
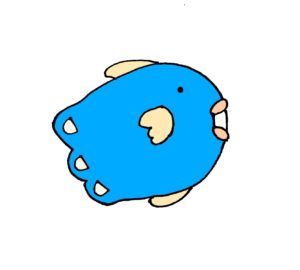
お寺と言えば、やっぱり釣り鐘よねえ。
ということで、神社とお寺の違いの一つが鐘、というわけだ。
.jpg)
梓

おお、たしかに!
釣り鐘は梵鐘(ぼんしょう)とも言う。
仏事の予鈴や、朝夕の時報に加えて除夜の鐘としても有名だね。
仏事の予鈴や、朝夕の時報に加えて除夜の鐘としても有名だね。
.jpg)
梓
初詣は神社? お寺?
ところでマンボウちゃんは、初詣は神社とお寺のどちらのイメージかな?
.jpg)
梓
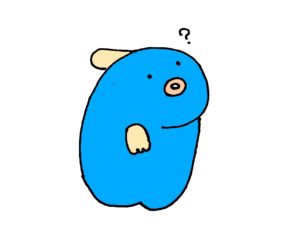
はて。お寺に行っている人もいるみたいですけど、マンボウちゃんは神社のイメージですかねえ。
「三社参り」という言葉もありますし。
ああ、でも、除夜の鐘はお寺だし……
ああ、わからないまぼねえ!
実は、どっちでもいい。
そもそも、初詣自体が、明治時代以降に生まれた最近の風習なんだ。
そもそも、初詣自体が、明治時代以降に生まれた最近の風習なんだ。
.jpg)
梓

はて、そうなんですか!
実は、結論を先取りして言えば、「初詣」は鉄道の誕生と深くかかわりながら明治中期に成立したもので、意外にも新しい行事なのである。
この新しい行事が定着してしばらくたって、後を追うように明治末期以降に俳句の世界に「初詣」という季語が登場したわけで、古句のなかに「初詣」という言葉が見つからないのもそのためなのである。
平山昇(2012)『鉄道が変えた社寺参詣 – 初詣は鉄道とともに生まれ育った』 (交通新聞社新書)
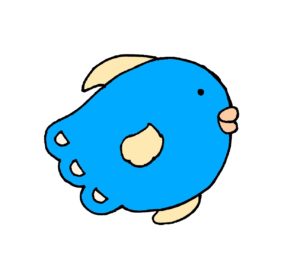
つい最近にできた風習だったんですねえ。
御朱印は神社と寺で分ける? 分けない?
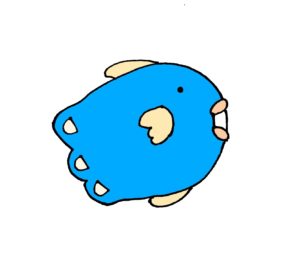
そういえば、御朱印を集めている人もいますけど、神社と寺で御朱印帳は分けた方がいいマボか?
それは人の好みかな。
神社と寺がいまのようにはっきりと分かれたのは明治以降の話。
昔は、神さまと仏さまは同じような存在として考えられていたんだ。
この神と仏を一緒と考える「神仏習合」の話は、このシリーズの最後に紹介するよ。
神社と寺がいまのようにはっきりと分かれたのは明治以降の話。
昔は、神さまと仏さまは同じような存在として考えられていたんだ。
この神と仏を一緒と考える「神仏習合」の話は、このシリーズの最後に紹介するよ。
.jpg)
梓
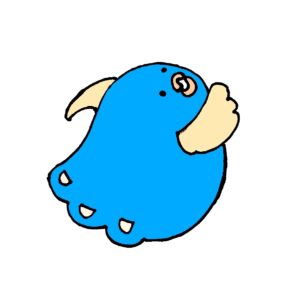
「神社とお寺で「御朱印帳」は分ける?分けない?一緒だと断られる?」(初心者の為の御朱印ガイド)
御朱印にまつわるあれこれは、こちらのブログが詳しかったのでご紹介させてもらいますマボ~
御朱印にまつわるあれこれは、こちらのブログが詳しかったのでご紹介させてもらいますマボ~
まとめ
- お寺では、「如来」「菩薩」「明王」「天」といった仏を拝む
- 総門、山門をくぐるときは合掌してから
- 手水舎でのお清めは神社と一緒
- お寺といえば釣り鐘!
- 初詣の起源は明治時代、神社に行ってもお寺に行ってもOK!
関連記事
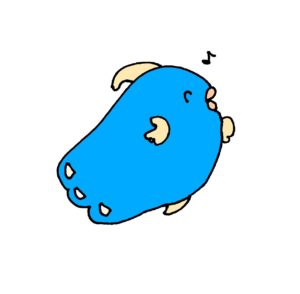
「神社とお寺の違い」
のシリーズをまとめてます。みんな、チェックしてくれ~。
参考文献
- エイ出版社編(2012)『お寺の基本』(エイ出版社)
- 平山昇(2012)『鉄道が変えた社寺参詣 – 初詣は鉄道とともに生まれ育った』 (交通新聞社新書)