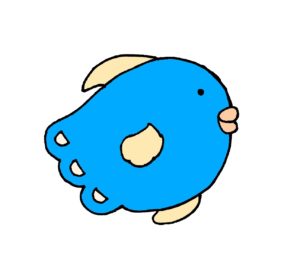
今回は、「千体千手観音」で名高い京都・三十三間堂の記事の続きです。
前回の記事では、ずらりと並ぶ観音像の前で圧倒されたマボねえ。

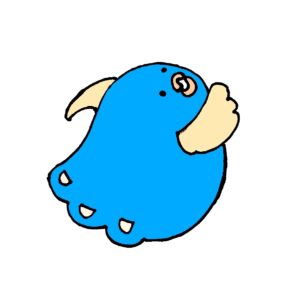
【三十三間堂①】千手観音1001体!│慶派・院派・円派が生んだ仏像の森へ
前回までの記事はこちらをチェックしてくれ~
.jpg)
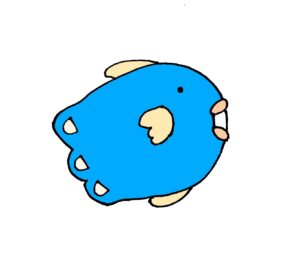
「二十八部衆(にじゅうはちぶしゅう)」こそ、
観音さまを守り支える精鋭チーム。
今日はその二十八部衆を紹介していくよ。
.jpg)
二十八部衆とは?
.jpg)
古代インドに起源をもつ神々で千手観音に従って仏教と、その信者を守るとされます。
二十八部衆の尊名や像形は、経説により違いはありますが、当院の諸仏は一具として揃っている希な作例です。
いずれも檜材の寄木造り、玉眼を用いた彩色像で、それぞれが迫真的な表情や姿態を見せる鎌倉彫刻の傑作です。
出所:蓮華王院 三十三間堂「二十八部衆像」(2025年11月4日確認)
.jpg)

①如来
②菩薩
③明王
④天
という4つの種類に分かれるけど、
二十八部衆は④天に属する。
天と呼ばれる仏像たちは、仏教におけるボディガード集団。
インド神話を中心とした神々が仏教に取り込まれ、天部になったんだ。
.jpg)
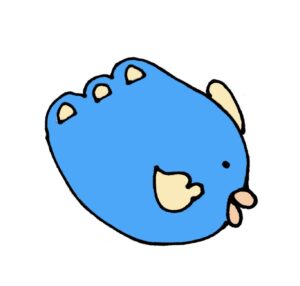
こちらの記事をチェックするマボよ~
二十八部衆の紹介
ちなみに、2018年7月、学術的調査に基づき、この二十八部衆像及び風神・雷神像について、配置変更と尊名(呼び名)の一部見直しが行われた。
過去の本に載っている尊名とは異なる場合もあるから注意してね。
.jpg)
金剛力士

出所:蓮華王院 三十三間堂「二十八部衆像」(2025年11月4日確認)
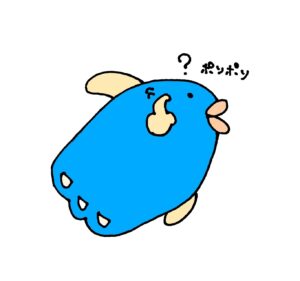
寺院に立つ金剛力士と同一視されることもあり、
那羅延天堅固に由来する金剛力士像が作られることもあるんだ。
もう一体の「密跡金剛(みっしゃくこんごう)」とペアになって仁王像をなしていることも多い。
.jpg)

出所:蓮華王院 三十三間堂「二十八部衆像」(2025年11月4日確認)
四天王
四天王としては持国天・広目天・増長天・多聞天という呼び名が有名なんだけど、三十三間堂では別名の尊名で呼ばれている。
.jpg)
- 東:提頭頼吒王(だいずらたおう)=持国天

- 西:毘楼博叉(びるばくしゃ)=広目天

- 南:毘楼勒叉(びるろくしゃ)=増長天

- 北:毘沙門天(びしゃもんてん)=多聞天

出所:蓮華王院 三十三間堂「二十八部衆像」(2025年11月4日確認)
インド神話のヒーロー
ヒンドゥー教では、
インドラは戦いの神として多くの物語に登場するし、
創造神ブラフマーはヴィシュヌ神やシヴァ神と共に三大神に数えられる。
しかし、仏教では、護法神として取り扱われているんだ。
.jpg)
- 帝釈天王(たいしゃくてんおう)

- 大梵天王(だいぼんてんおう)

出所:蓮華王院 三十三間堂「二十八部衆像」(2025年11月4日確認)

龍王と金毘羅
このナーガが、東アジア・東南アジアへ仏教・インド文化が伝わる過程で、
「蛇→大蛇→龍・水神」
と要素が変容していった。
結果、日本においても、「龍王(りゅうおう)」という訳語・表現が使われるようになったんだ。
.jpg)
- 難陀龍王(なんだりゅうおう)

- 娑伽羅龍王(さがらりゅうおう)

出所:蓮華王院 三十三間堂「二十八部衆像」(2025年11月4日確認)
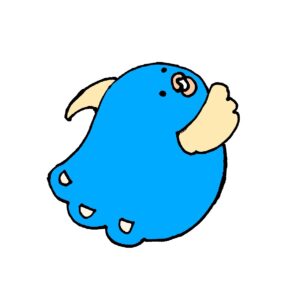
かっちょいいじゃないのよ~。
元々はガンジス川のワニの神「クンピーラ」に由来するんだけど、
水の神として、日本においては海上安全や豊漁とも結びつきが強いね。
.jpg)
- 金毘羅(こんぴら)

出所:蓮華王院 三十三間堂「二十八部衆像」(2025年11月4日確認)
そのまんま鳥

出所:蓮華王院 三十三間堂「二十八部衆像」(2025年11月4日確認)

そのまんまの鳥が出たマボ!
これまではなんだかんだ、蛇に由来する、ぐらいだったのにい。
インド神話の鳥の王であるガルダに由来するんだ。
ちなみに、不動明王の背中では炎が燃えているのが定番だけれど、
この背後の炎は、迦楼羅が羽を広げた姿に似ていることから「迦楼羅焰」(かるらえん)」と呼ばれるんだ。
.jpg)
戦いの神
戦いの神ということもあって、ここでは引き締まった表情と緊張感で表現されている。
興福寺の優しい表情の阿修羅が有名だけれども、
多くの阿修羅像はこのような厳しい顔をしているんだ。
.jpg)

出所:蓮華王院 三十三間堂「二十八部衆像」(2025年11月4日確認)
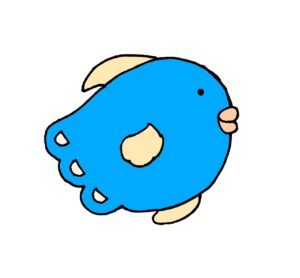
観音さま千体だけでも圧巻なのに、さらにこんな頼もしい仲間たちが守ってたとは!
観音さまの足元の二十八部衆もじっくり眺めてみれば、きっとお気に入りの「推し護法神」が見つかるはずだ!
.jpg)
まとめ




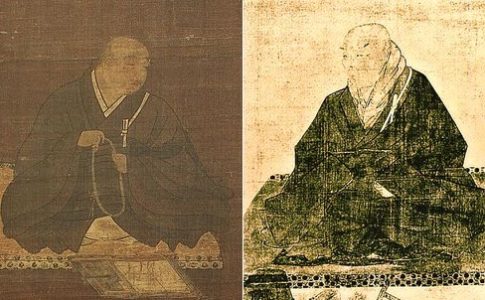







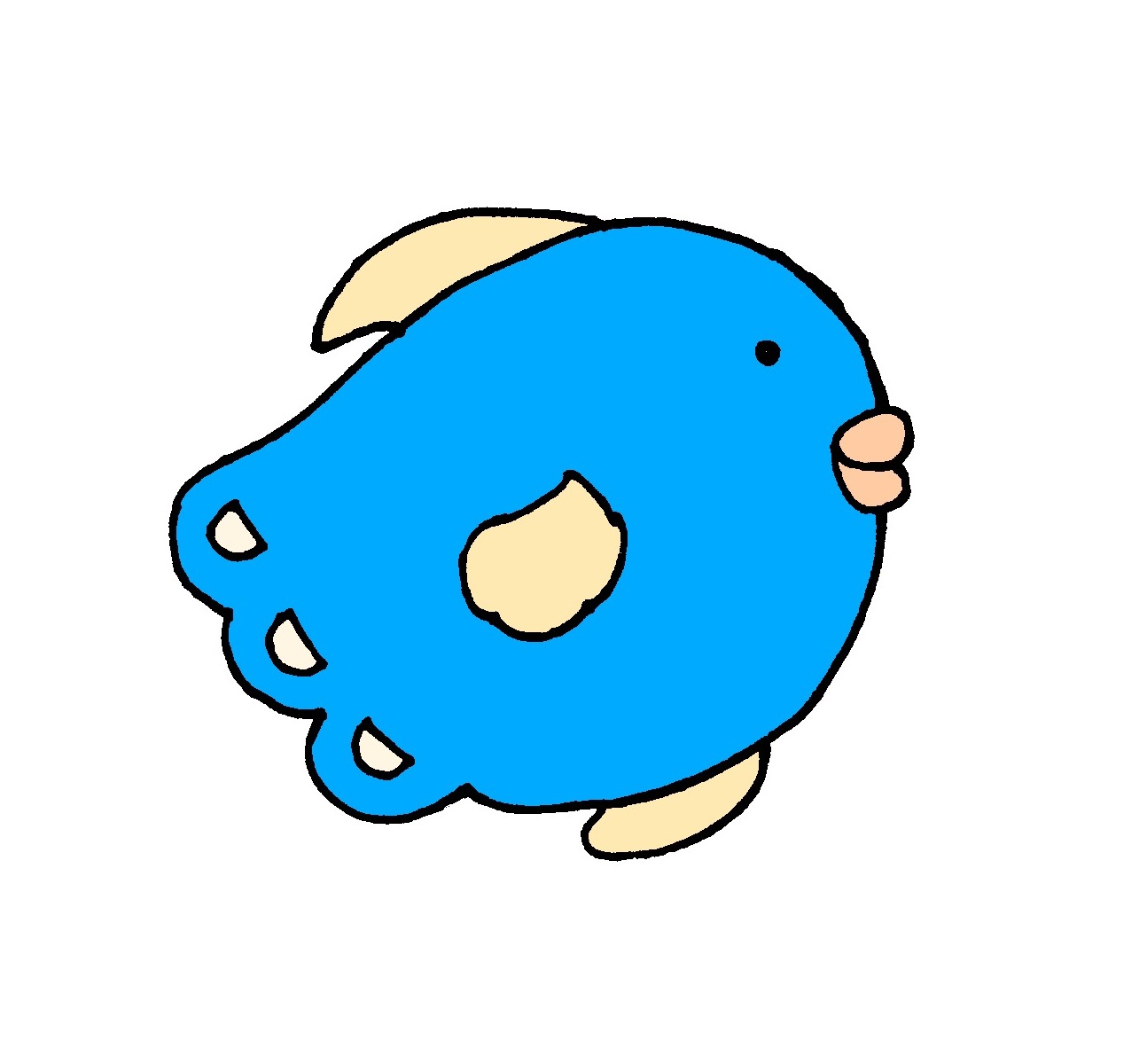
コメントを残す